
脳出血は、脳の内部にある細い血管が破れ、脳内に出血する病気です。被殻、視床、橋、小脳、皮質下という部位によく起こることが知られています。一方のくも膜下出血は、多くの場合、脳の表面にある太い血管にできた動脈瘤(血管のこぶ)が破裂することにより生じます。
脳出血やくも膜下出血でよく見られる症状は、突然生じる頭痛や嘔吐です。脳出血の際には、出血した脳の部位に応じた症状が出現します。左右どちらかの手足の麻痺・しびれ、顔の表情のゆがみ、話しにくさ、めまいなどが比較的頻度の高い症状です。出血量が多い場合には、意識障害がみられ、最悪の場合は死に至ることもあります。
脳出血の主な原因は高血圧です。脳の血管の奇形なども脳出血の原因になり得ます。くも膜下出血を引き起こす脳動脈瘤の原因は、高血圧、動脈硬化、喫煙、遺伝的要因とされています。
脳出血やくも膜下出血を診断するために最も重要なのが、頭部CTや頭部MRI等の画像検査です。この検査によって出血量や出血部位などを確認していきます。出血が確認された場合は、出血部位を詳しく調べるため、カテーテルを用いた血管造影が行われることもあります。
脳出血やくも膜下出血が確認された場合、厳重な血圧の管理が必要です。必要に応じて、手術が行われます。出血により生じた症状を緩和させるため、リハビリテーションも行われますが、残念ながら後遺症が残ってしまうこともあります。
脳出血が起きると、手足の麻痺・話しにくさなどの後遺症が残ることが多くあります。くも膜下出血をひとたび発症すると、社会復帰できる確率は僅か3分の1とされています。脳出血とくも膜下出血に共通した、最大の危険因子は高血圧です。適切な降圧治療を行うことで、出血のリスクを下げることができます。
脳梗塞とは、脳の血管が詰まり血液が送られなくなることで、脳が壊死してしまう病気です。
脳梗塞でよくみられる症状は、左右片側の手足に急に力が入らなくなる、顔の表情がゆがむ、呂律が回らない、言葉が出ない、物が二重に見える、感覚が鈍くなる、めまいがするなどです。脳梗塞が広範囲に及んだ場合には、意識障害も出現します。脳出血やくも膜下出血とは異なり、頭痛が出現する頻度は高くありません。
脳梗塞は大きく3種類に分類されます。①アテローム血栓性脳梗塞、②ラクナ梗塞、③心原性脳塞栓症の3つが、代表的な脳梗塞の病型です。
動脈硬化が原因の脳梗塞です。動脈硬化が起こると、血管の内腔が狭くなります。狭くなった内腔で血栓(血液の塊)が形成されることにより生じる脳梗塞です。高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などが原因になります。一過性脳虚血発作と呼ばれる脳梗塞の前兆が、20-30%に認められることが知られています。
脳の奥深くで起こる脳梗塞です。脳梗塞になる範囲は小さく、症状も比較的軽いという特徴があります。主な原因は高血圧です。
心臓でできた血栓(血液の塊)が脳の血管へ流れ着き、血管を詰まらせてしまうために起こります。心臓でできる血栓は大きいことが多く、広範囲の脳梗塞を起こします。症状は突然出現し、意識障害を伴いやすいことも特徴です。3種類の脳梗塞の中では、最も重症度が高くなります。
心原性脳塞栓症は、心臓で血栓ができることで生じます。血栓ができる原因として最も多いのが、心房細動です。心房細動では心房内で血液がよどみ、固まりやすくなります。そこで血栓が形成され、脳塞栓症を起こすことが多くみられます。
頭部CTや頭部MRI等の画像検査を行います。脳梗塞と脳出血は、症状だけでは区別がつきにくい病気です。画像検査を行うことで、確実な診断をつけられます。脳梗塞が確認された場合、血管内治療を行うこともあります。その際は、カテーテルを用いた血管造影検査も必要です。
脳梗塞の治療としては、血液をサラサラにする治療(抗血小板療法や抗凝固療法)が行われます。また発症早期の場合には、血栓を溶かすt-PAという薬剤を使用することがあります。このt-PAは劇的に症状を改善できる可能性のある薬剤です。しかし、出血のリスクも大きくなることから慎重に使用しなければいけません。他にも、血管に詰まった血栓を回収するために、血管内治療を行うこともあります。
アテローム血栓性脳梗塞の原因は動脈硬化です。動脈硬化を予防することが、脳梗塞の予防にもつながります。そのため、動脈硬化の原因となる高血圧、糖尿病、脂質異常症を改善させることが重要です。まずは食事療法(減塩にする、カロリーを控えめにする、脂っこいものを控える)や運動療法を行いましょう。また、喫煙も重要な動脈硬化の原因です。喫煙をされている方は、禁煙にチャレンジしてください。
一方、心原性脳塞栓症の最も多い原因は、心房細動です。まずは心房細動にならないよう、血圧の管理を適切に行う必要があります。もし心房細動になってしまい、血栓(血液の塊)ができるリスクが高い場合は、血液をサラサラにする抗凝固療法を行って脳塞栓症のリスクを下げることができます。

著者上原和幸
循環器専門医、総合内科専門医、内科指導医。日本医科大学医学部卒業。日本赤十字社医療センターで初期研修(内科プログラム)を行う。同院循環器内科で勤務後、日本医科大学付属病院 総合診療科 助教に着任。日本赤十字社医療センター循環器内科 非常勤医師を兼務。
主な資格
循環器専門医、総合内科専門医、内科指導医、臨床研修指導医、日本赤十字社認定臨床医、日本病院総合診療医学会認定医、日本旅行医学会認定医

〒272-0021
千葉県市川市八幡3-26-1 ガレ本八幡1F
047-324-1114
WEB予約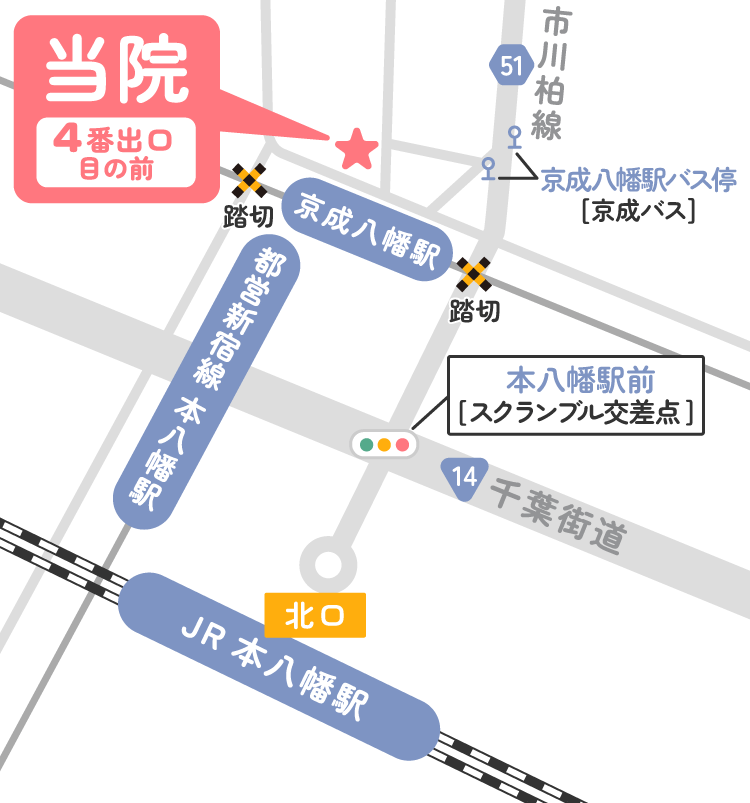
2022.6.19
【脳機能分類】mRSとCPCの比較表
modified Rankin Scale (mRS)、Cerebral Performance Category (CPC)の比較表を作りました。脳梗塞や心停止…Read More
2022.5.08
【意識レベル評価】JCS・GCSとは?意識障害時の対応は?
意識レベルの評価方法、JCSとGCSについて解説します。JCSとGCSの見やすい一覧表も掲載しています。意識障害…Read More
2022.3.13
【若手の先生必見】循環器専門医の配合剤を意識した高血圧薬物療法
降圧薬の種類が多すぎて何を使えばいいか分からない・・・そんな方は、配合剤を意識して降圧薬を選択すると…Read More
2022.2.03
【高血圧】降圧薬配合剤の一覧表【2022年版】
降圧薬の配合剤、中身の成分が分からずにお困りですか?診療をしていると困る場面が多くあります。カルシウ…Read More